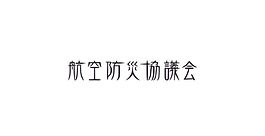top of page

航空防災協議会について
令和6年 航空防災元年の幕開け
令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」は、我が国の災害対応において空域活用の重要性を浮き彫りにしました。半島という地形特性により、道路網が寸断され、孤立地域が多数発生。これに対し、民間ヘリコプターを含む航空資源が、物資搬送・人員輸送・情報収集など多方面で活躍しました。
航空防災協議会の設立とその意義
令和6年8月1日、全国10自治体を発起人として、全国の自治体首長が参画する「航空防災協議会」が設立されました。これは、空域を活用した災害対応力の強化を目的とした全国的な枠組みであり、自治体・民間・国の連携による新たな防災モデルの構築を目指しています。
航空防災協議会の活動
主な活動内容
•空域活用に関する制度設計と実証実験
•地域特性に応じた防災訓練の実施と事例共有
•航空資源(ヘリ・ドローン等)の活用方法の教育・啓発
•場外離着陸場など地域資源の整備・活用
地域防災力の再定義
航空防災協議会では、地形・交通網・人口分布など地域ごとの特性を踏まえた災害対応力の向上を図っています。特に、孤立地域への迅速な支援や、空からの情報収集・指揮系統の確立など、従来の地上中心の防災体制を補完・強化する役割を担っています。
「空からの防災」が地域の命を守る
令和6年能登半島地震を機に、災害時の空域活用は「最後の砦」から「第一の選択肢」へと進化しつつあります。航空防災協議会は、令和6年を「航空防災元年」と位置づけ、制度・実装・教育・連携の各面から、空からの防災力を地域社会に根付かせる取り組みを進めています
お問い合わせ
bottom of page